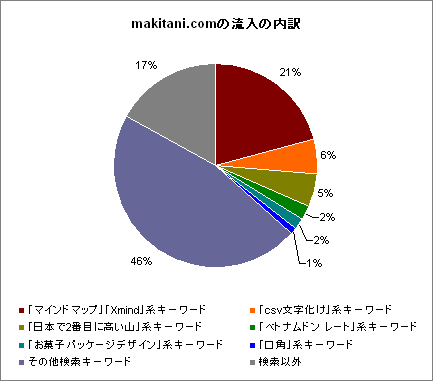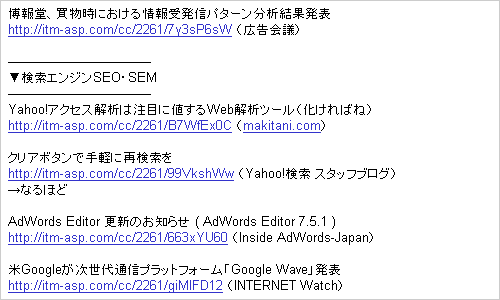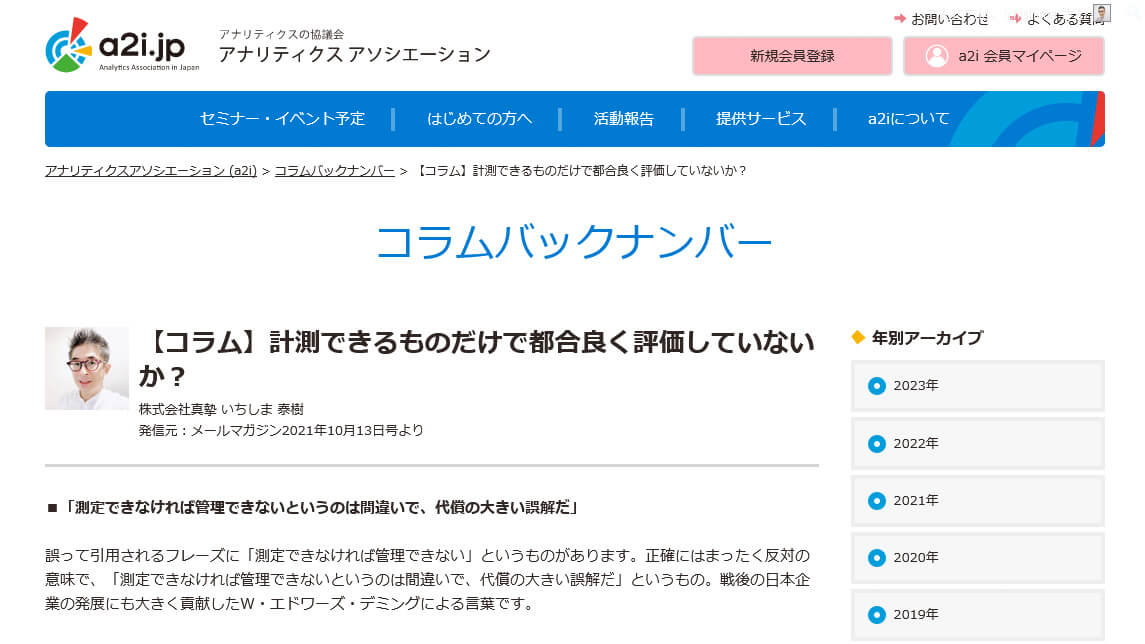
セミナー編成委員会としてアナリティクス アソシエーションの活動に携わっているのですが(それはこれからも続くのですが)、アナリティクス アソシエーションでの「執筆陣によるローテーションでのコラム執筆」を終えました。
振り返れば14年間も担当していました。執筆したコラムは165件。お読みいただきありがとうございました。
ということで「乾いたタオルを絞るように書いたコラムから選ぶ、15の文章」と題して、書いたコラムの中から印象に残っているものやメッセージとして変わらないものをピックアップしました。
新しいものから過去のものへと遡っていきます。