
気付いたらインターネットの情報流通の首根っこのかなりの部分をTwitterに握られてしまっていたかもしれない。

Twitterのタイムラインが災害時に時系列じゃなくて困る件、僕もなんとかしてほしいと思っている1人だけれど、グローバルな仕様なのであきらめつつ、僕は「emergency」という名のリストを作って回避している。
このようなアカウントを放り込んで、非常時にはときどき確認する。リストなので時系列で表示されるし、他アカウントがいいねしたツイートも差し込まれない。RTは含まれるけれど、まともなアカウントならRTも信頼できる情報が中心になる。
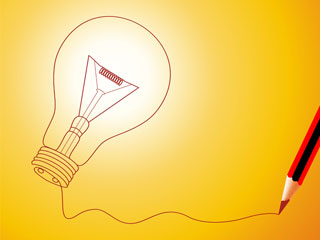
仮説を立てるということ。あるいは気づくということ。状況から仮説を立てて結果を分析することは結構あっても、ある程度の結果から仮説を見つけて改めて状況を分析し直すというフローは案外むずかしいんじゃないかなと思います。
漫然とTwitterのタイムラインを眺めて、興味深い法則に気がついた。
それは、500人以上フォロワーのいるユーザーの大半は、「フォロワー数 / 被リスト数」がおよそ10という値になる。ということだ。
この法則の「10:1」が正しいのかはさておき、Twitterの「フォロワー数」と「被リスト数」の割合に法則性があるのではないかと気がつくところがうらやましくもあります。細かいことを言えば、「被リスト数」はユニークではないので(同じ人から複数のリストに入れられることもある)、「フォロワー数<被リスト数」になる可能性も物理的にはあるのですが、それを「フォロワー数500人以上」とフォロワー数の母数をある程度確保することで、回避しているのだろうな、と。
とまれ、「指数」として非常におもしろいと思います。
それでも、Twitterのフォロワー数が1,000人の人と10,000人の人では、同じ指数でもまた意味やニュアンスが異なってきますよね、きっと。フォロワー数が10,000人のように大人数になると、この指数は下がってくるのでは?(リストの機能をよく知らないユーザーが多くなってくるでしょうから)。
僕は、フォロワー数が866、被リスト数が145なので、指数は約「6」でした。えーっと、「ある業界の権威とかご意見番」って、そんな恐ろしい…。しがないフリーランスなのですが…。でもなぜか被リストは多いよなと感じてました。全然僕からはフォローしてなくて恐縮なのですが。
自分が理解できないものには「なぜこんなものが流行るのか」と思ってしまうもの。従来型のメディアには、Twitterだってソーシャルメディアだって(少し前だとブログやCGMも)、「なんだか流行っているが、所詮○○だろ」と自分の中の固定観念で上から目線で片付けてしまいたくなるようなものかもしれません。
でもね、2002年か2003年に「ウェブログ」「ブログ」という存在を知った僕も、そんな「ブログ」なんてものは流行らないよと思ってました。1999年頃から僕は「テキストサイト」というカテゴリーで呼ばれていたサイトをやってましたが、「それとどう違うのかね?」と、半ば「ブログ」というバズワードに敵対心すら覚えていました。2003年11月に登場したライブドアブログで初めて「ブログ」をやってみて、「一緒やん」という結論でいまに至るのですが。
LTV(顧客生涯価値)というキーワードは僕はこれまであまり使わなかったので、言葉として使い方がちょっとわかっていない。
ブログでもコミュニティでもTwitterでもソーシャルメディアの中の何かでもなんでもいいのですが(リアルものでももちろん)、対話者、購読者、フォロワー、顧客との関係性を良好なものにし、LTVを最大化させていくという視点が、今後よりいっそう大切になってくるのではないかなと思います。いやいまでも十分そこを踏まえていると思いますけれども。
最短距離で買わせる、とりあえずクリックさせる、ページビューを稼ぐ、そういった即時性即効性を求めたり、目の前の利益に注力したものは、少しずつゆるやかに「主流ではなくなる」のではないかな、と。消費行動が慎重になってきているのもありますし、どのジャンルでもトップ層の独占のような感じになっている中、「より深い関係性を持つ」「愛される」というのが、企業であれ個人であれ、視点として持っておかなければいけないところじゃないかなと思います。
昨日の朝、Twitterでの「ドロリッチなう」のネタにグリコからお礼が来たというのがニュースになっているのを見て、昼にはコンビニでドロリッチを買ってしまっている僕がいました。「あ、ドロリッチ」という条件反射で。
「グリコ乳業の菓子、ドロリッチを今食べています」という意味の投稿「ドロリッチなう」がツイッター上で大流行。投稿をカウントする自動実行プログラム(ボット)や、独自のイラストが次々に制作されている。ブームを受け、グリコ乳業は今月、ボットやイラストを制作したユーザーに感謝のメールを送った。新商品も合わせて贈られたユーザーは、新商品バージョンのイラストを作る様子をリアルタイムでネットで生放送、「ドロリッチなう」の波はさらに拡大している。
おもしろいと思うのは、グリコ側がTwitter側に歩み寄ってきたというところ。大企業が、なんだかまだわからない「Twitterとやら」に「ありがとう」を言おうと思った、というところが素敵。担当者が思ったのか、誰かが進言したのか、とにかくある程度の上層部がOKを出したというのがすごいな、と。でも、実際にTwitterに降り立って「ありがとう」と言ったわけじゃないみたいだけどね。
Twitterでの「ドロリッチなう」は、一般的なレベルで見れば局地的なほんの小さな花火で、たぶんそれほど売上には貢献していないはずです。なので、新商品まで送るレベルの感謝といえばクエスチョンマークなのですが、でもその結果こういう形でニュースになり、それを見た僕も条件反射で買ってしまっている。PR効果。
いいタイミングでTwitterがバズワードというのもありますが、でもたぶんドロリッチそのものの中毒性とワンアンドオンリーなところが一番のキーだと、僕は思います。あれは確かにたまに飲みたくなるわ。
Twitterはコミュニケーションのツールではあるのですが、企業によるTwitterの活用で、「一方通行の情報発信bot」として利用する可能性はあるのでしょうか。
よく見ると、東急線の公式アカウントらしきものが、、、なるほど企業のTwitter活用としてはなかなかいい感じですね。
確認したわけではなく僕の推測ですが、それは東急の公式のTwitterアカウントではないのでは?と思います。公式のアカウントであったならごめんなさい。